情動の機構と歴史的考察(Mechanism of Emotion, a Historical Consideration) |
川村光毅、小幡邦彦
Key words: second signal system, a triune brain, evolution/dissolution, hierarchy,
psychosis
抄録
近代科学の確立以降の情動に関する考え方の流れを知り、異常心理学や精神医学との具体的、戦略的接点を見出すべくこのテーマを選んだ。その動機は、昨年9月に生理学研究所で行われた、"情動・記憶・意欲をいかにとらえるか"と題する研究会での討論に遡る。そのうち、記憶に関するものは本誌(19/12)特集号でも採り上げられているので、この号には、研究会での発表のうちで、主として、情動・意欲に関するものが掲載されている。神経科学および精神医学の多方面の分野から執筆されている最新のデータは、いわば、鳥が飛行する上で必要な空気であるが、個々の事実を大局から見通して学ぶことも大切なことである。デカルト、ベルナールが背負っていた弱点を克服して、この約百年の間に提唱されたパブロフの言語信号系、マクリーンの三型階層性脳説、ジャクソンの階層理論、エーの器質・力動論をわれわれは単に解釈して満足するのではなく、そこからも新しい武器を構築する素材を発見したいと思う。
1.はじめに
2.デカルトの情念論
3.感情、情動の発現機構と神経回路に関する考察
4.精神神経医学における諸機能の階層的秩序(ヒエラルキー)とその崩壊
5.精神分裂病1,5,9,15,19)と躁欝病4,9,10,15)における情動・意欲の障害
6.文献
近年、神経科学は大いに進展し、知・情・意の心理複合体である"心"の問題は現在の重要な研究課題である。それを高次神経活動の所産として捉えることが基本とならねばならない。そして、その異常として精神病の発症機構、病態生理を究明していく必要がある。割り切っていうと、「知」は大脳新皮質・海馬、「情」は扁桃体・視床下部、「意」は帯状回・辺縁系に大きく関連するようである。そのほかに、前頭前野を中心とする皮質連合野、視床下部・下垂体を主座とする液性調節系、ドパミン、セロトニンを含む汎性投射系など考察の視野を広げた上で精神活動という研究課題を追求することが現在求められている。現在、これらのアミンやGABAのレセプター、トランスポター、合成酵素の遺伝子ノックアウトマウスで情動行動の異常を主徴とするものが次々と得られている。この特集号では、情動・意欲を中心に執筆されているが、神経科学および臨床精神医学の研究者が多方面から討議し問題点を明らかにする上での出発点と位置づけたいと願った。今後、研究対象の的を絞って、①情動に関わる神経回路の構築とその生理機能、②情動発現とその病態に関わる遺伝子とその制御、③情動障害と神経伝達、細胞内情報伝達系の諸分野を推進する必要があるかと思う。このために、情動・意欲の機構の解明を意図する基礎科学者と精神の異常に悩む人間に直面している精神医学者との接点を大局的にみいだし、そこからの発展を願って、昔を掘り起こして明日を読んでみたい。

 デカルト(Rene Descartes, 1596-1650)は、中世スコラ哲学の実証性と明証性に欠ける学問体系を疑い、思考の合理性を尊重して、物理学と数学の方法論を用いて思考し、ヨーロッパ近代思想の核心を示す人間理性の独立を宣言した。かくして彼は近代科学の礎を確立した。今日われわれは、脳と情動に関する近代科学的研究のスタートとしてデカルトの「情念論」3)を位置づけることができるかと思う。
デカルト(Rene Descartes, 1596-1650)は、中世スコラ哲学の実証性と明証性に欠ける学問体系を疑い、思考の合理性を尊重して、物理学と数学の方法論を用いて思考し、ヨーロッパ近代思想の核心を示す人間理性の独立を宣言した。かくして彼は近代科学の礎を確立した。今日われわれは、脳と情動に関する近代科学的研究のスタートとしてデカルトの「情念論」3)を位置づけることができるかと思う。
デカルトは、「精神ないし心」には物質的実体がなく、その「精神」が松果体を介して「脳」をコントロールすると考えた。デカルトは、動物一般の身体を、脳も含めて、力学的法則に従って働く機械とみなした。ヒトと動物を区別するものは「精神」の有無であった。デカルトの情念論によると、感情は「機械的な」自動反応である。すなわち脳に運ばれた感覚信号は意識に昇ることなく自動的に評定され、そして、前、中、後の3つの"脳室"に貯えられている気体ないし液状の霊気である「動物精気(esprits
animaux)」が、そこから中空の神経の管を通して、身体に送られて骨格筋や腺に働き、自律的な反応が起こる。因みに、「霊気」ないし「精神の気」の営みで感覚や運動が起こるという精神の座に関する脳室局在論の思想は、ガレノス(Galenus)以降約1300年間を支配した中世の暗黒時代の継承であった。
この身体的反応の信号が脳室の中央に位置する松果体へと運ばれる。そこで、松果体が「精神」とコミュニケートする。こうして初めて「感情」あるいは「情動」が体験されることになる。かくして、「精神」は松果体を介し、脳を含む身体全体をコントロ-ルすることができる。
デカルトのモデルは力学的あるいは機械論的であり、心身二元論である。「脳」と「精神」の関係で言えば、「精神」は脳の活動
/
働きの所産ではなく、物質を離れた存在となっている。一方、「脳」は身体の一部である。松果体は「脳」と「精神」のいわば、仲介(interface)の役割を果たしている。ここで、種々の感覚刺激が脳内で評価をうけ自律的な反応を起こすが、その過程で情動が誘発されると想定したことは、デカルトの卓見であると言ってよいであろう。
しかし、デカルトをよく読んでみると、彼が機械と比較して論じているのは動物の身体であって(動物機械論)、精神を持つ人間は動物とは区別されている。言語を使用する人間だけが理性的精神(あるいは霊魂)をもっているとする"人間に関する心身二元論"が骨子である。にもかかわらず、生物科学史上でのデカルトの意義は大きい。
人間の理性と真理を重視したデカルトの合理主義の近代思想は、クロード・ベルナール(Claude
Bernard,1813-1878)によって発展し、強化された。彼はデカルトの約一世紀半あとに活躍した実験医学の基礎を築いたフランスの生理学者であるが、現象を追求する上での絶対的デテルミニスム(絶対的決定論:無生物におけると同様に生物体においても、すべての現象の存在条件は絶対的に決定されていると考える立場)を指導原理とした2)。ベルナール自身は、他方で、キリスト教的信仰の旗をかざし、その中世の世界観から脱却しきれなかったけれども、彼は、科学における仮説と実証という方法を生物学の分野に導入し、再現しうる実験事実のみによって生物学的事象を語る、という方法論を生物学の基本として、科学的研究を行なう近代生物学を確立した。
ベルナールを出発点とした19―20世紀の生物科学は、2つの方向に発展していった。1つは生理学にはじまり、物理・化学法則による内的環境そのものの理解つまり生化学・生物物理学への道であり、もう1つは同じく生理学、とくに神経生理学から出発して、キャノン(後述)らに至る内的環境維持機構―
ホメオスタシス(homeostasis)― への道であった。
 ベルナールの研究室で、反射運動を抑制する神経中枢の実験的研究を行ったイワン・ミハイロヴィッチ・セーチェノフ
(И.М.Сеченов,1829~1905)は、帰国後、これらの実験にもとづいて「脳の反射」(1863)を発表した。彼は、ヒトも含めて高等動物の脳の活動が反射の特徴のうちの二つをもつことを、すなわち反射のはじまりは感覚器官への刺激作用にあり、反射の終わりは筋肉の活動にあるということを論証した。次に、感覚器官への刺激作用の後で、且つ筋肉の活動の開始前に起こる事象が脳内における結合によって説明ができるかどうか、また、思考や情動が反射によって解釈されうるかどうか、を考察した。セーチェノフは脳のなかに、反射の新しい局面つまり「筋肉的局面」を強化したり制止したりする機能をもつ一定の中枢の存在を想定した。彼は情動を、強化された"筋肉的反応"という言葉で説明した20)。彼の研究上の指導原理は、世界の物質的統一性、決定論であり、脳の活動に反射原理をひろげ、動物およびヒトの精神活動の反射理論の発端となり、パブロフの高次神経活動の学説を生み出すのに道をひらいた。事実、パブロフは彼の研究の出発点を「セーチェノフの<脳の反射>が出版された年(1863年)」と言っている。
ベルナールの研究室で、反射運動を抑制する神経中枢の実験的研究を行ったイワン・ミハイロヴィッチ・セーチェノフ
(И.М.Сеченов,1829~1905)は、帰国後、これらの実験にもとづいて「脳の反射」(1863)を発表した。彼は、ヒトも含めて高等動物の脳の活動が反射の特徴のうちの二つをもつことを、すなわち反射のはじまりは感覚器官への刺激作用にあり、反射の終わりは筋肉の活動にあるということを論証した。次に、感覚器官への刺激作用の後で、且つ筋肉の活動の開始前に起こる事象が脳内における結合によって説明ができるかどうか、また、思考や情動が反射によって解釈されうるかどうか、を考察した。セーチェノフは脳のなかに、反射の新しい局面つまり「筋肉的局面」を強化したり制止したりする機能をもつ一定の中枢の存在を想定した。彼は情動を、強化された"筋肉的反応"という言葉で説明した20)。彼の研究上の指導原理は、世界の物質的統一性、決定論であり、脳の活動に反射原理をひろげ、動物およびヒトの精神活動の反射理論の発端となり、パブロフの高次神経活動の学説を生み出すのに道をひらいた。事実、パブロフは彼の研究の出発点を「セーチェノフの<脳の反射>が出版された年(1863年)」と言っている。

 イワン・ペトローヴィッチ・パブロフ (И.П.Павлов,1849-1936)
は彼の条件反射学説16,17,18)のなかで、人間がもつ三つの高次神経系を区別し、強調した。三つの神経系とは、第一に、皮質下領野に位置する無条件反射あるいは「本能」の体系、第二に、大脳皮質に位置する第一信号系あるいは感覚信号系、第三に、これもまた皮質に位置する第二信号系あるいは言語信号系である。
イワン・ペトローヴィッチ・パブロフ (И.П.Павлов,1849-1936)
は彼の条件反射学説16,17,18)のなかで、人間がもつ三つの高次神経系を区別し、強調した。三つの神経系とは、第一に、皮質下領野に位置する無条件反射あるいは「本能」の体系、第二に、大脳皮質に位置する第一信号系あるいは感覚信号系、第三に、これもまた皮質に位置する第二信号系あるいは言語信号系である。
無条件反射系より高次にある体系は個体が獲得した反射活動で、これによって個体は行動する。そしてパブロフによって条件反射と名づけられた。第一信号系ないし感覚信号系は感覚的、想像的で思考も原始的で情動的である。そして、環境の影響を直接受けて働いている。また、有機体の内的環境からの刺激も受けとっている。
人間が環境的条件に適応する過程での最高の体系は、環境からの信号を処理する第二信号系あるいは言語信号系である。それは認知の段階としては理性的なものである。そこでは、第一信号系の感覚像と評価されたその意味とが、相互に結びつけられる。パブロフはこれを「人間のみにあるより高次の心性」と表現した。
以下に、第一信号系と第二信号系の両信号系の性質と両者の関係とについて重要な点を一言述べておきたい。問題の中心は情動と思考の性質と役割にある。
動物は環境からの信号を処理する第一信号系に限られている。動物の情動は、皮質にある感覚信号系と皮質下にある無条件反射系の関係が重要な一側面となっている。動物の情動は、皮質過程と皮質下過程の条件結合によって決定される反応で、換言すれば、第一信号系と生得的反射の相互関係の本質的特徴を含んでいる。この意味で、動物の活動はつねに単なる情動的活動と言える。
これに対して、人間にとっては、情動は意味をもっている。つまり、概念[化]あるいは言語による抽象作用が加わっている。情動と概念[化](あるいは論理的認識ないし思考)とは、意識のもつ異なる側面である。<概念>の役割は、事物や過程を周囲の世界に反映することである。他方、<情動>の役割は、概念のうちに反映された事物が個人に対してどんな意味をもつかを評価することである。したがって、すべての思考過程は、多かれ少なかれ情動的色調をもっている。
以上述べてきたように、パブロフによれば、情動と概念あるいは認識およびそれらの相互関係の基礎にある高次神経活動は、三つの体系を含んでいる。それは、皮質にある感覚信号系と言語信号系、皮質下にある無条件反射系である。思考はつねに言語による抽象作用であるので、第二信号系あるいは言語信号系が思考ないし概念化の基礎をなす神経活動となる。他方、情動は、主として第一信号系あるいは感覚信号系と皮質下の無条件反射系の相互作用である。このように、思考過程と情動の基礎にある神経諸過程は密接に関係しあっている。
A.キャノン (Cannon) の「情動発現の座」とパペッツ(Papez)の「情動回路」
大脳皮質を除去した動物でも、情動反応が起きることが示された(Goltz,
1892)後、情動の中枢を皮質下に求める実験が行われた。すなわち、ネコの脳の切断実験結果、間脳を含む皮質下組織の残存が怒りの反応を起こすに必要であることが明らかにされた。キャノン(1927)は皮質下組織(とくに視床)が情動の座であり、視床から「情動の衝動」が起こり、それを大脳皮質が抑制すると考えた。(後に脳切断研究の結果、情動の座は視床ではなく視床下部であると修正された。)
キャノンはホルモンを神経とならんで生命機構の中心に押し出そうとした。彼はベルナールがmilieu
interieurの安定性と表現したものを、さらにしっかりした生理学的な事実の上に立って、ホメオスタシスということばで表わすことを提案した。しかしホルモン学は、キャノンによってその重要性がクローズアップされながら、その生命機構論の積極面を長い間充分にはひろげることができなかった。
Papez(1937)は更に、臨床データも考慮して、情動回路モデルを提唱した。彼は、感覚入力は視床で中継されて、視床下部へ伝わり、そこで情報処理を受けた後、下行性と上行性に伝えられるとした。下行性伝導は脳幹および脊髄へ向かい、とくに、自律的反応を起こす。上行性に向かうものは、視床下部乳頭体→視床前核→帯状回→海馬傍回→海馬→脳弓→乳頭体という閉回路(すなわち情動回路)を形成し、入力に関する「情動的」信号処理が行なわれると考えた。また、彼は帯状回皮質を情動の情報の受容部位と考えた。パペッツの回路モデルの特徴は、視床下部へは二つの経路からの感覚情報が入力され、一つは、直接に視床下部に入り、その情報はそこで処理され情動的意味が付加されるが、他は、大脳皮質で処理されたのち視床下部に到達する高度の「情動的色彩」を帯びた感覚情報も存在するとしている点である。
B.マクリーン (Paul D. MacLean) の「内臓脳」/「辺縁系」と「三型階層性脳」説 (図1)
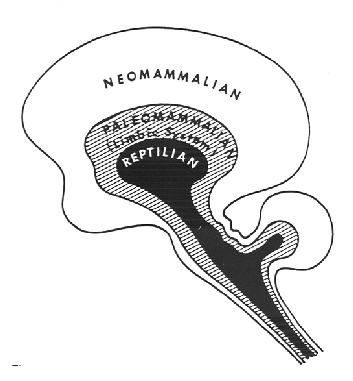 マクリーンは、辺縁皮質およびそれと神経結合している皮質下組織を辺縁系(limbic
system)と呼び、情動および内臓機能に関与する1つの機能系とする概念を提唱した11)。彼はまた、辺縁系が自律機能に密接に関連しているので、これを内臓脳(visceral
brain)とも呼んだ。マクリーンのモデルにおける情動発現のセンターは広義の"海馬体"(海馬回、歯状回および扁桃体を含んだ領域)である。海馬体からの出力は視床下部を介して情動反応と自律反応を発現させるとした。
マクリーンは、辺縁皮質およびそれと神経結合している皮質下組織を辺縁系(limbic
system)と呼び、情動および内臓機能に関与する1つの機能系とする概念を提唱した11)。彼はまた、辺縁系が自律機能に密接に関連しているので、これを内臓脳(visceral
brain)とも呼んだ。マクリーンのモデルにおける情動発現のセンターは広義の"海馬体"(海馬回、歯状回および扁桃体を含んだ領域)である。海馬体からの出力は視床下部を介して情動反応と自律反応を発現させるとした。
また、マクリーンは恒温動物の脳に3型のシステムから構成される階層性(ヒエラルキー)を考えた12,13)。いわゆる三位一体脳説(a hierarchy of three brains in one―a triune brain)と言われるもので、原始爬虫類脳(protoreptilian brain)、旧哺乳類脳 (paleomammalian brain) と新哺乳類脳(neomammalian brain)である。原始爬虫類脳は、脳幹、間脳、基底核よりなり、旧哺乳類脳は辺縁系に相当し、新哺乳類脳は新皮質をもっている。ここで、動物の古い脳の上に新しい脳が付加されるという進化の方向の道筋と人間の精神の構成の生物学的基盤が示されている。
原始爬虫類脳(reptilian)は、原始的な学習や記憶に基づいた、型にはまった行動を現わす。そして、この行動は個体維持と種族保存に基本的なものである。魚類や爬虫類では、大脳基底核が最高の行動運動統合部位で大脳皮質は未発達である。これらの動物の行動反応は辺縁系と視床下部で開始され、そのパターンは柔軟性に乏しいステレオタイプ型である。パブロフ流に言えば、無条件反射の体系によって行動する段階である。
我流に解釈すれば、感覚入力としては、嗅覚のみ前脳の一部の嗅脳と原始的な辺縁脳に直接入るが、味覚、触・圧覚、平衡覚、視覚、聴覚などは、脊髄・脳幹レベルでの反射機構で処理され、能動的出力への仲介(または統合中枢)は原始的な大脳基底核と視床・視床下部であろう。ここで言う基底核は、運動系の他に原始的な側坐核や扁桃核を含んだ未発達段階の構造物と考えられる。
旧哺乳類脳(paleomammalian)は哺乳類において初めて発達した。この脳部位には情動の座があり、rigid/stereotypicな原始爬虫類脳の働きを、ある程度、柔軟に制御している。げっ歯類や下等哺乳類でも辺縁系と視床下部が反応発現の主体となっている。辺縁系と視床下部は行動発現の開始部位の一つである。すなわち、「情動過程」そのものに基づく行動発現と結びついている。この段階の動物は、人間と共通した情動の原型を明瞭にもっていると言えよう。また、パブロフの条件反射学説に従えば、第一信号系による反射活動の体系が備わる段階と言える。
今風に解釈すれば、古い皮質から一部に発生した爬虫類にみられる新皮質(general
cortex)は領域的に広がり、大脳感覚野や側頭葉を主体とする後連合野からの辺縁系脳部位に対するコントロールが見られるようになる。
新哺乳類脳(neomammalian)は高等哺乳類においてみられる発達した前脳の外被である。新皮質は、外界環境因子をクールに分析し、高度の精神活動を行なう。霊長類になると、大脳皮質(とくに感覚野と連合野)、小脳、大脳基底核が著しく発達し、ここに行動発現に対する「認知過程」の関与が入ってくる。この過程で、道具の使用を学んだサルたちが表象能力(かって知覚されたことのある像を、その対象が現に感覚器官に与えられているという条件がない場合にも再生する反映能力)をもちはじめる。新皮質と辺縁系との相互連絡は動物が高等になるにつれて発達し、とくに側頭連合野・前頭前野と辺縁系構造物(海馬、扁桃体、視床下部を含む)との間の線維連絡は密になり、情動行動とその基盤はさらに複雑になり、質的にも異なったより発達したものとなる。ヒトでは新たに言語野が発達し(サルからヒトへの大脳皮質言語野の発達については、川村6,7,8)を参照)、言語は個体および集団間のコミュニケーション手段として大きな役割を果たすようになる。つまり、抽象概念を用いた思考が可能となり、情動状態を自省し、洞察できるようになる。言語はいわゆる第二信号系であり、特定の生物学的刺激および対象的経験にしばられている感覚信号系とは区別される。このように意思疎通の手段としての言語が形成された段階までくれば、人間による環境の反映、すなわち人間の意識の発生について語ることができる。それは、脳の発達の成果であると同時にその脳を持った動物の社会生活の発展の産物でもある。次項に述べる精神の発達と障害の考察は、この段階の脳の保有者、人間、を対象にしたときにのみ成立するものである。
さらに管見を述べれば、ここでは辺縁系に対する前頭前野の支配と「思考過程」の「情動状態」への関与が特徴的で、解剖学的にも連合野と視床下部・扁桃体との直接的または間接的(嗅内野を介して)結びつきは格段に強くなっている。

4.精神神経医学における諸機能の階層的秩序(ヒエラルキー)とその崩壊
イギリスの神経学者ジャクソン (John Hughlings Jackson, 1835~1911)はSpencer(1820-1903,進化が全自然の本質的な事象であるとする進化哲学を提唱した。獲得形質の遺伝を進化要因として重視した)の進化論哲学の影響をうけて、「階層理論」すなわち「神経系統の進化・進展(evolution)と解体・退行(dissolution)」の思想を展開した(1884)。ジャクソンによれば神経系の進化とは、特定の秩序を有する上行性発達であり、より単純で次元の低い機能(組織化された、自動的な、低次の中枢)から、より複雑で高次元の機能(組織化されていないで、出生後に組織化されつづけることになる、随意的な、高次の中枢)へと移行・発展するものであるとした。そして、その頂点をなすのが「精神の器官」(organ of mind)、または意識の身体的基盤であると考えた。
このように神経系統は階層構造(hierarchy)をなしている14)。ところが神経系統の病的解体ないし退行は進化の過程を逆行する。つまり退行は最高次の中枢から低次の中枢へとすすむ。そのとき陰性症状(または一次症状)と陽性症状(または二次症状)が区別され、前者は退行によって起こった上位の水準の機能の欠損症状であるが、後者は病的過程によって破壊をまぬがれた下位の水準の機能の解放症状である。ジャクソンは神経疾患と精神病とを統一した原理によって理解しようと試みた。彼は解剖・生理・精神医学などの学問があまり開拓されていなかった当時の状況下で、進展と退行の階層構造を解剖学的・生理学的基礎によって秩序づけを行なった(たとえば、前角細胞/脳幹運動核/線条体/皮質運動領など)。蓋し慧眼と言うべきである。
ジャクソンの解体の概念は後世に大きな影響を与え、エー(Henri Ey, 1900~1977)によって新ジャクソニズム(neo-jacksonisme)として展開された。エーは ジャクソンの神経機能の進化と解体の理論を精神医学に適用したといわれているが、他方、フランスの伝統であるジャネ(Pierre Janet,1859~1947、エーの師で「心的緊張 tension psychologique」の概念を提唱し、精神諸機能の階層的秩序づけを行なった)とフロイト(Sigmund Freud,1856~1939、意識の深層にある特殊な、不可知的な心的力が、心的過程を支配しているとみて、ここから精神分析なる理論をつくりあげた。かれは、性的本能と、これを抑圧する力とを、機械論的に説明した)との折衷であるとも見られている。エーによって精神疾患とはその原因において常に器質的であるとともに、その病的発生において常に心理的であるとされた(器質・力動論organo-dynamisme)。エーの説は注目に値する見解を含んでいるが、その生理学的基盤に対する証明が不明瞭である。このように、彼はジャクソン学説にしたがって心的存在(l'etre psychique)が解体して低い水準に低下したものが精神病であると考えた。そして、症候論的立場から精神病を分類した。
5.精神分裂病1,5,9,15,19)と躁欝病4,9,10,15)における情動・意欲の障害
ブロイラーBleulerは精神分裂病の中心的特徴として4つのA,すなわち、 Association(連合)、Affekt(感情空虚)、Autismus(自閉)、Ambivalenz(両価)を挙げた。分裂病患者は一般に自閉的で、この自閉世界に安住して、感情意欲のない状態が長く続くと欠陥分裂病となる。感情の鈍さ、無関心、奇妙な行動、意欲の減退がある。感情意欲の減退を主症状とするものに破瓜型があるが、その他に、緊張型、妄想型がある。
ところで、分裂病の精神疾患障害は、海馬・扁桃体-視床下部-連合野が関連する辺縁系の情動制御の障害を中軸とするものとして把えていくことができないだろうか。両価性(ambivalence)といって、二つの正反対の感情や欲求が同時に存在する。つまり、愛と憎、欲望と無欲のように一つの対象に関しての二つの逆の評価が同一個体内に同時に存在する。肉親の半身として観たモーゼとアロンのように、相反する性格と相対立する思想に随伴する情動と意欲が葛藤しながら出没する。この対立した評価の同時性と撞着は、扁桃核の機能異常を推量させる。
神経解剖学的には、前頭葉と側頭葉・辺縁系の間には、(1)前頭前野と辺縁葉皮質・扁桃核の間の単あるいは多シナプス経由の両方向性投射、(2)パペッツの回路、(3)両皮質領域から側坐核に投射し、側坐核から淡蒼球、視床背内側核を経て再び前頭前野へ返る回路があり、これらの経路に発達過程で結合不全が起こると考えられる。また、神経発達期における障害が原因であるとする仮説も非常に魅力的である。細胞構築上の異常が、認知、情動、記憶機能に関連する側頭葉内側部、前頭葉、前部帯状回などに観察されるが、グリオーシスは見いだされていない。脳の侵襲に対する組織修復反応は妊娠中期以降になって初めて起こる出来事であるので、これらの領域にグリオーシスの証拠を見いだすことができないということは、妊娠初期に起こった何らかの侵襲に対応する組織変化と解釈される。海馬の神経細胞の配列異常や嗅内野の皮質上層細胞群の異所性は、皮質への細胞移動が胎児期5カ月末には終了する事実からすると、妊娠4,5カ月までに加わった脳への侵襲に基づくと考えられている。分裂病発症に関する生化学的仮説については省略するが、今後、扁桃体中心核や側坐核などについて慎重に検証することが望まれる。このように、分裂病は前頭葉・側頭葉をも包括する情動辺縁系の障害、それも、神経細胞の移動や細胞死が起こる時期の神経発達期の"より複雑で次元の高い階層に属する機能(ジャクソン流)"の障害で、かつ、パブロフ流に言えば、第二信号系の不可逆的な崩壊を暗示している。
これに反して、もう一つの二大精神病である躁鬱病には、生物学的深刻さは浮き彫りにされておらず、崩壊には至っていない第二信号系(パブロフ流)の解放ないし抑制であろう。ジャクソン流のヒエラルキーの位置づけは比較的に"より単純で次元の低い"ものであろう。躁鬱病は爽快と憂欝、行動の増減(興奮と抑制、思考-言語行動なら奔逸と抑制)が対をなす主症状を呈する。躁病では爽快と興奮、鬱病では憂鬱(不安)と抑制が組になっている。この躁欝病にみられる情動障碍は、分裂病にみられるそれとは質的に異なったものである。前者はバランスは崩れているが感情は<ずっしりと重く、厚みがあり、人間的なもの>が感じられる。後者は対照的に<砕けやすく、薄脆で不人情的>で定型を失っている。躁欝病は、辺縁系および連合野―視床下部-脳下垂体を主座とするアミン/ペプチド系の分泌調節の障害が気分変調の基調をなすものと思われる。事実、臨床的にモノアミン系の神経終末にあるトランスポーターやモノアミン酸化酵素が抗鬱薬の作用点であることが知られている。さらに想像をたくましくすれば、神経細胞とくにモノアミン・ニューロンのphenotype が決まり 、その数も決定した後の発達期の障害、すなわち、ホルモンや伝達物質とそれらの受容体(レセプター)の数量のバランスが決定される時期における、脳内の比較的に広範囲の障害であろう。
本疾患の本態を考えてみるに、脳幹のアミン系、とくにインドールアミン(セロトニン)系の機能調節異常および視床下部-脳下垂体-副腎皮質系(HPA系)、-甲状腺系(HPT系)、-性腺系(HPG系)を主とするホルモン分泌調節障害による機能異常という諸要素の変調が基盤になっているものと考えられ、種々の仮説が提唱されている。脳梁下領域における形態異常の所見も報告されている。
一般に、情動行動における海馬・中隔(外側中隔)系の機能は、経皮質性の感覚情報を変換して、快感をもたらす脳幹情動系を駆動し、逆に怒りや恐れをもたらす脳幹情動系に対しては抑制すると考えられている(例、動物における外側中隔の破壊あるいは電気刺激の所見)。一方、扁桃核系の機能は、海馬・中隔系とは、情動行動に関しては一見逆の機能、すなわち、そのような感覚入力を受けて怒りや恐れの脳幹情動系を駆動・促進し、性行動や食行動を抑制しているように思われる。扁桃核を含めた側頭葉を両側性に破壊されたサルにみられるKluver-Bucy症候群としてよく知られているところである。無条件反射性の情動反応を基にした条件反射の形成に扁桃核系が関与していると考えられる。
鬱病の症状が進行すると、生の喜びや愉悦の感情表出が乏しくなるだけでなく、怒りや恐れ(恐怖)の情動も外見上抑制され、情動のあらゆる面が沈澱しているかのようにみえる。食欲や性欲といった欲動も減退する。これらの事実は、鬱病においては、快感や食欲、性欲に対して促進的に働いている海馬・中隔系の機能が低下しているだけでなく、怒りや恐れを促進している扁桃核系の機能も抑制されていることを示唆している。
臨床医学から久しく遠ざかっている基礎医学徒が、神経科学と精神医学の間の実体ある架橋を構築しようと将来に期待して、非難を覚悟で書いた、文字通りの拙論である。ピエロを自認してはいるが、建設的な批判も同時に望んでいる楽天家でもある。

1) 秋元波留夫 (1996) :
分裂病の最新研究―精神から分子レベルまで― 監訳 創造出版
2) Bernard, C. (1865) : Introduction a L'etude de la Medecine Experimentale.
三浦岱栄 訳 1938 実験医学序説 岩波書店
3) Descartes, R.(1649): Passions de L'ame 野田又夫 訳 1974
情念論、中央公論社
4) Drevets, W.C., Price, J.L., Simpson Jr., J.R. et al. (1997) : Subgenual prefrontal
cortex abnormalities in mood disorders. Nature, 386: 824-827.
5) 池田研二、黒木規臣、入谷修司 (1997) :
精神分裂病の形態学的研究. 精神医学、39: 570-582.
6) 川村光毅 (1977): "連合野"の線維結合 (I) 皮質間結合
ーサルとネコの皮質間結合の比較と"連合野"の発達についての試論ー
. 神経進歩 21: 1085-1101.
7) 川村光毅 (1993) : 認知機能についての機能解剖学的考察.
生物学的精神医学(小島、大熊編)第4巻 認知機能からみた精神分裂病 183-198.
学会出版センター.
8) 川村光毅 (1998) : 神経情報の統合:条件反射と高次機能. 脳と神経―分子神経生物科学入門―(金子、川村、植村編)、第3章、共立出版、印刷中
9) 神庭重信、川村光毅 : 分裂病と躁欝病.
脳と神経―分子神経生物科学入門―(金子、川村、植村編)、第4章、共立出版、印刷中
10) 神庭重信 編 (1995) :
躁うつ病の脳科学―方法論から臨床研究まで―、星和書店
11) MacLean, P. D. (1954) : Studies on limbic system ("visceral brain") and
their bearing on psychosomatic problems. In: Recent Development in Psychosomatic Medicine
(R.Cleghorn and E.Wittkower eds.) pp.101-125. Pitman, London.
12) MacLean, P. D. (1967) : The brain in relation to empathy and medical education.
J.Nerv. Ment. Dis., 144: 374-382.
13) MacLean, P. D. (1982) : On the origin and progressive evolution of the triune brain.
In: Primate Brain Evolution: Methods and Concepts (E.Armstrong and D.Falk eds.)
pp.291-316. New York, Plenum Press.
14) 中田 修 (1966) : 深層心理学(二) 層学説. 異常心理学講座 1.
みすず書房
15) 脳と精神の医学 (1997) 8巻、4号 特集:脳の世紀と精神医学の展望
16) Pavlov, I.P. (1927) : Lectures on the Activity of the Cerebral Hemisphere,
Leningrad. 林 髞 訳、1937. 条件反射学
―大脳両半球の働きに就いての講義― 三省堂; 川村 浩 訳、1975.
大脳半球の働きについて― 条件反射学― 岩波書店.
17) Pavlov, I. P. (1927) : Conditioned Reflexes, An Investigation of the Physiological
Activity of the Cerebral Cortex. (Transl. & Ed. by G.V. Anrep) Oxford Univ. Press.
18) パヴロフ選集 (1962)
上巻、下巻 (コシトヤンツ編、東大ソ医研訳)合同出版社
19) Schizophrenia Bulletin (1997) Vol.23, No.3, Issue theme: The Neuroanatomy of
Schizophrenia.
20) Sechenov, I. M. (1952-1956) : Selected Physiological and Psychological Works, prepared
for print by the Academy of Sciences of the U.S.S.R., Moscow.
図の説明
図1.マクリーンの脳の3つの基本型で階層性を示している。哺乳類前脳が進化の過程で一部がヒトの脳に継承される。「辺縁系」ないし「内臓脳」は旧哺乳類脳に相当し、情動行動に関係する。

校正時に追記
1.扁桃体と前頭葉眼窩面皮質:この間の相互結合の機能的意義の解釈は重要(Nature,
Neuroscience, 1/2: 1998)で、鬱状態の患者でこの系に異常に高い局所血流量を示す所見(Science,
275: 1586-1592, 1997)などが得られている。
2.前脳とくに辺縁系について:新皮質、古皮質、線条体、扁桃体を包括する前脳と視床下部の発達および動物の進化を視野に入れた、これらに関与する遺伝子を探索する研究はbreakthrough をつかむ第一歩となろう。線条体( lateral and medial ganglionic eminences )および扁桃体の発生学的研究は重要である。本論文に引用したMacLean の図1には、原始爬虫類脳にlimbic system が描かれていないが、扁桃核と視床下部を結ぶ情動経路である分界条などが発達して認められる(J.comp.Neurol.,384: 537-555, 1997)ことからも、腹側線条体・側坐核をふくめて、トカゲの類においても階層性から言って低い段階の情動機構が存在することは明らかである。条件反射の用語を使えば、このような原始的な基本構造の上に動物進化の過程で、感覚信号系、さらには、言語信号系が付加されて、高次の情動機構が形成されることになる。精神病にみられる情動障碍をこのような視点から把握できないだろうか。
3.精神の階層性の問題:第Ⅲ章でジャクソンとエイの学説を紹介したが、力不足のため平坦な内容でその関連や流れについての記述も表面的である。現在までに集積された神経科学の土壌の上に立って改造し、変革することにより、新たに本質に迫るものを再構築することができよう。 文献:1)Ey, H. (1975) Des idees de Jackson a un modele organo-dynamique en psychiatrie. 大橋、三好、浜中、大東 共訳 :ジャクソンと精神医学、みすず書房、東京、1979 . 2)Ey, H. 、石田卓訳編:精神疾患の器質力動論、金剛出版、東京、1976. 3)三浦岱栄:ジャクソンとネオ-ジャクソニズム. 異常心理学講座 10. みすず書房、東京、1965.
4.パブロフの実験神経症:内村(精神医学の基本問題、1972)はこれを高く評価し提要を残している。このイヌを用いた実験神経症の研究論文は、"精神"疾患のモデル動物を作製する際の必読の文献であろう。
5.最後に、筆者の一人、川村は「精神保健指定医の証」の保持者であることを友人の忠告をいれてここに記す。

脳と科学(星和書店) 20 (1998) 709-716、より許可を得て転載